触りすぎは髪のSOS!抜毛症とセルフケアの落とし穴
「あ、また触ってる…」
※当サイト内アフィリエイト広告等が表示されます
気づけば無意識に頭を触っていませんか?髪をかき上げたり、指で毛先を弄んだり、頭皮をカリカリと掻いてしまったり。多くの人にとって、それはただの癖かもしれません。しかし、その“ちょっとした癖”が、やがて**抜毛症(トリコチロマニア)**という深刻な問題に発展する可能性があることをご存知でしょうか?

抜毛症は、自分で自分の髪の毛を抜いてしまう衝動制御障害の一種です。ただの癖と侮るなかれ、放っておくと薄毛が進行したり、頭皮にダメージを与えたりするだけでなく、精神的な苦痛を伴い、日常生活にも支障をきたすことがあります。
Table of Contents
なぜ頭を触りすぎてしまうのか?
「まさか、たかが頭を触るくらいで抜毛症になるなんて!」そう思うかもしれません。しかし、抜毛行為は往々にして、日常的な頭を触る癖からエスカレートしていくケースが少なくありません。
では、なぜ私たちは頭を触りすぎてしまうのでしょうか?
1. ストレスや不安の解消

人間はストレスを感じると、それを和らげるための行動を無意識に求めることがあります。頭を触る行為は、その一つ。落ち着かない時や集中したい時、手持ち無沙汰な時に、頭や髪に触れることで一種の安心感を得ようとするのです。これは、貧乏ゆすりや爪を噛む行為と同じような、**セルフハーミング(自傷行為)**の非常に軽度な形とも言えます。
2. 習慣化された行動
最初は軽い気持ちで始まった頭を触る行為も、繰り返されるうちに習慣化されます。テレビを見ながら、考え事をしながら、スマートフォンを操作しながら…気づけば当たり前のように頭に手が伸びている。こうなると、もはや意識して止めようと思っても、なかなか止められない状態になってしまいます。
3. 髪や頭皮への過度な関心
髪の毛の状態が気になって頻繁に触ってしまう人もいます。枝毛を探したり、フケがないか確認したり、あるいは単に手触りの良い髪を撫でていたり。美容に対する意識が高い人ほど、髪に触れる機会が多くなる傾向があるかもしれません。しかし、この過度な関心が、逆に抜毛行為へと繋がるリスクをはらんでいます。
触りすぎが抜毛症を引き起こすメカニズム
では、頭を触る癖がどのように抜毛症へと発展していくのでしょうか?そのメカニズムは、主に以下の3つの段階を経て進行すると考えられています。

段階1:触覚刺激による快感と依存
頭皮や髪の毛に触れることは、心地よいと感じる人もいます。特に、緊張している時や不安な時に触れると、一時的にストレスが軽減されるような感覚を覚えることがあります。この快感が繰り返されることで、脳は「頭を触る=快感・安心」と学習し、その行動を求めるようになります。
段階2:特定の毛への執着と抜毛行為の出現
習慣的に頭を触る中で、特定の「気になる毛」を見つけることがあります。それは、手触りの悪い毛、うねった毛、白髪、あるいは単に「ここにあると気になる」といった、ごく些細な理由かもしれません。最初は指で弄ぶ程度だったのが、やがてその毛を「抜いてしまいたい」という衝動に駆られるようになります。そして、実際に抜いてしまうと、一時的に達成感や解放感を得ることがあります。これが、抜毛行為の始まりです。
段階3:抜毛行為の強化と習慣化
一度抜毛行為を経験すると、それがストレスや不安を解消する手段として脳にインプットされてしまいます。ストレスを感じるたびに、無意識のうちに頭に手が伸び、気になる毛を探し、そして抜く。このサイクルが繰り返されることで、抜毛行為はますます強化され、やがて自分の意思ではコントロールできない強迫的な行動へと変化していくのです。
抜毛症に陥ると、抜いた毛を眺めたり、触ったり、中には口に入れてしまう人もいます。また、抜毛行為中は、一種のトランス状態に入り、自分が何をしているか意識が希薄になることもあります。
抜毛症から抜け出すためのセルフケアと専門家への相談
もし、あなたが頭を触りすぎる癖に心当たりがあり、それがエスカレートして抜毛行為につながっていると感じるなら、以下のセルフケアを試してみてください。
1. 自分の行動を記録する
いつ、どのような状況で頭を触ってしまうのか、または髪を抜いてしまうのかを記録してみましょう。ノートに書き出したり、スマートフォンのメモ機能を使ったりするのも良いでしょう。**行動のトリガー(引き金)**を特定することで、その状況を避ける、あるいは代替行動をとるヒントになります。
2. 手持ち無沙汰を解消する
ストレスを感じた時や暇な時に頭に手が伸びやすいのであれば、その代替行動を見つけましょう。ストレスボールを握る、ハンドスピナーを回す、編み物をする、絵を描くなど、指先を使う別の活動を取り入れることが有効です。
3. 頭皮や髪への意識を変える
髪の毛を傷つけることへの意識を高めましょう。抜毛行為は、毛根にダメージを与え、将来的にはその部分から髪が生えなくなる可能性もあります。美容師に相談して、定期的なヘアケアを取り入れるのも良いでしょう。健康的で美しい髪を維持することへの意識が、抜毛行為を抑制する力になることがあります。
4. 環境を整える
抜毛行為に集中しやすい環境を避けることも大切です。例えば、鏡の前での抜毛行為が多いのであれば、鏡にカバーをかける、暗い場所で過ごす時間を減らすといった工夫も有効です。
5. 周囲に理解を求める
もし信頼できる家族や友人がいるなら、自分の悩みを打ち明けてみましょう。一人で抱え込むことは、精神的な負担を増大させます。周囲の理解とサポートは、回復への大きな助けとなります。
専門家への相談をためらわないで
しかし、セルフケアだけではなかなか改善が見られない場合や、抜毛行為によって日常生活に大きな支障が出ている場合は、心療内科や精神科、あるいは心理カウンセリングの専門家を訪れることを強くお勧めします。
抜毛症は、単なる癖ではなく、治療が必要な精神疾患の一つです。認知行動療法や薬物療法など、専門的な治療を受けることで、症状をコントロールし、回復への道を歩むことができます。
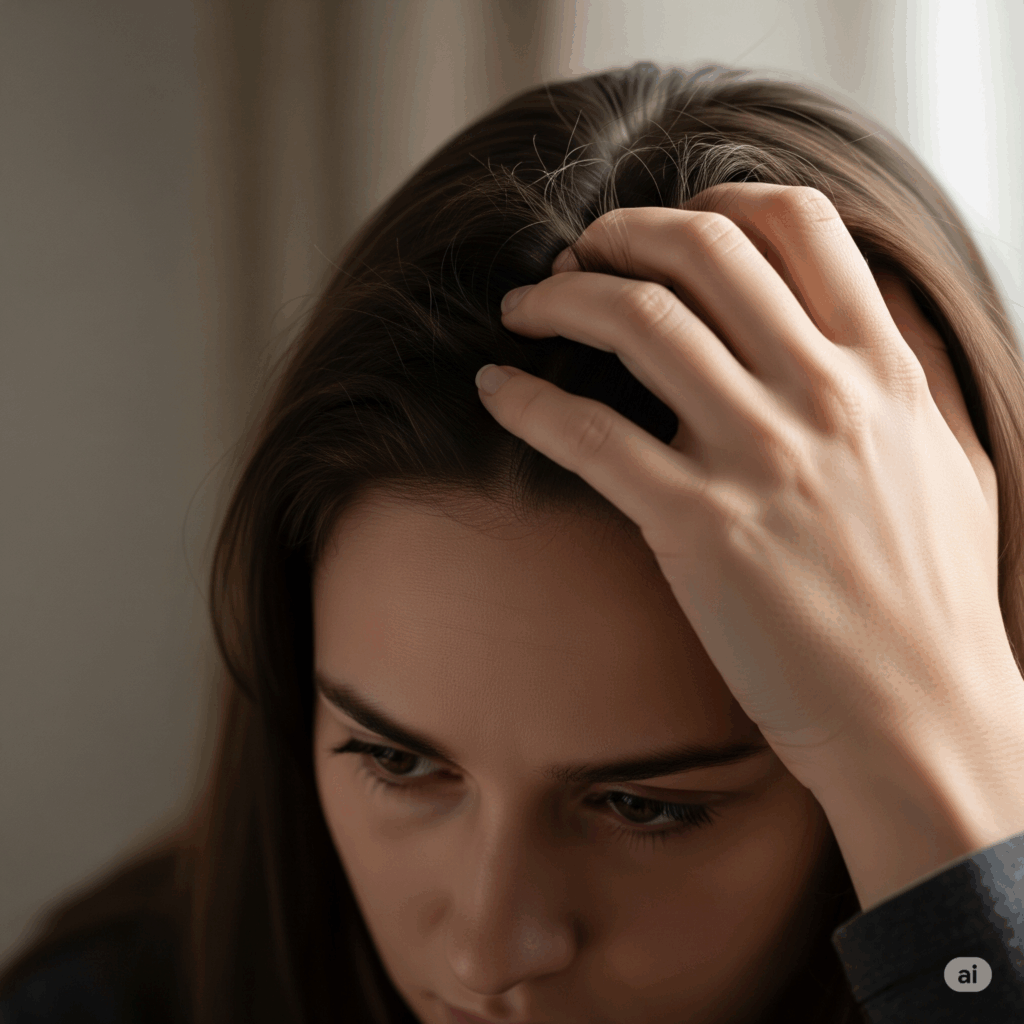
「こんなことで病院に行くのは恥ずかしい」「たかが癖だから…」とためらう必要は全くありません。早期に専門家のサポートを得ることが、回復への一番の近道です。
まとめ
頭を触る癖は、誰にでもあるものかもしれません。しかし、それがストレスや不安と結びつき、無意識のうちに髪の毛を抜いてしまう抜毛症へと発展するリスクをはらんでいます。
もし、ご自身や大切な人が頭を触りすぎる癖に悩んでいたり、抜毛行為がエスカレートしていると感じるなら、決して一人で抱え込まないでください。まずはご自身の行動を見つめ直し、セルフケアを試みる。そして、必要であれば、迷わず専門家の助けを求める勇気を持ってください。
あなたの髪と心の健康を守るために、今できることから始めてみましょう。


